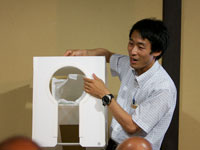第30回 海せん山せんの暮らし
第29回 地をおおうものの現在(いま)
第28回 極地を 生きる ちから
第27回 鮎香る川変更をプレビュー (新しいタブで開く)
第26回 甍(いらか)の波をおよぐ
第25回 虫に聴く
第24回 森を看る
第23回 つむぐ、まとう
第22回 京から食をみなおす
第21回 京のしまつ・世界のしまつ
第30回 海せん山せんの暮らし
日 時: 平成26年7月26日(土)午後4時~6時
挨 拶: 柴田昌三(地球環境学堂 教授)
美山から:「山の生き方-狩-」鹿取悦子氏(山里住民)
京大から:「海の生き方-鱸(すずき)-」山下洋(フィールド科学教育研究センター 教授)
司 会: 深町加津枝(地球環境学堂 准教授)
協 力: 嶋臺(しまだい)



今回の嶋臺塾は、美山の里から鹿取悦子さんをお招きし、山の暮らしの現在をご紹介いただきました。京都府南丹市美山町は、由良川の源流域にあり、萱葺き民家が残る集落や、原生林が残る京都大学芦生研究林で有名なところです。江戸っ子の鹿取さんは、大学院修了後、島根大学に勤められていたのですが、大学時代に魅了された美山に舞い戻られ、今はそこで暮らしておられます。美山では、観光農園 江和ランドで田んぼや畑、接客、NPO法人 芦生自然学校の一員として、自然や田舎に帰る活動などをされています。同時に、猟師として、現在の山里の営みにとっての悩みである有害鳥獣とも闘っておられます。杉の皮を剥いで枯らしてしまうクマ、樹皮・植林・灌木など、なんでも食べてしまうシカ、その他、イノシシ、カワウ、アライグマ、ハクビシン等々。それらの被害は、広がるというより、より「深く」なっているのだそうです。猟師への規制が強まる中、鹿取さん自身も猟銃を持ち、シカの解体場を作ったり、鹿肉メニューの開発などを行うことでこの問題に取り組んでおられます。山で暮らすと、自ずと季節の移り変わりに敏感になり、自然の異変にも気づくようになります。野生を取り戻し、想像力を働かせて生きることの大切さを教えていただきました。
大学からは、フィールド科学教育研究センターの山下洋さんに鱸(すずき)についてお話しいただきました。美山を源流のひとつする由良川は、京都府の面積の40%に渡る広範な流域を持ちます。その河口は舞鶴ですが、山下さんはそこを「丹後湾」と呼んでおられるそうです。今回は、その「丹後湾」あたりで暮らす鱸のお話しでした。山下さんは、鱸を海の鳶(とんび)に例えられます。鳶は、鷲(わし)や鷹(たか)と同じ猛禽類でありながら、他の猛禽類に比べてあまり人間からはありがたがられていません。これは、なんでも食べてどこにでも住む鳶のしぶとさによるもので、鱸もそれに似ているのだそうです。実際、日本沿海の漁獲量が激減する中、鱸だけは増えています。鱸は、海で産卵し、海で暮らしますが、その一部は川にも上ります。12~1月頃生まれた卵は、1~2月頃子魚となり、2~3月頃には稚魚となります。稚魚は、海岸から10mぐらいのところを回遊しますが、そのうち体の小さい稚魚は、由良川に雪解け水が流れ込む3月の頃、川を遡上します。そして、餌となるアミの多い川で育った鱸は、海だけで暮らす鱸よりも一回り大きな体となって海に戻ってくるのだそうです。山下さんは、魚の年輪である「耳石」を使って、そうした鱸の生態を調べておられます。会場では、皆さんその耳石を手にとってまじまじと見入っておられました。
町の方からは「京都の人は鱸はあまり食べませんなあ」と、高級魚の鱸が、それこそ鳶並みにあしらわれて、苦笑が出る場面もありましたが、シカやクマをどう食べるか、川に上った鱸の味や寿命、子供に殺生を見せるこなどについて、賑やかに質問や意見が交わされました。
海に千年山に千年住んだ蛇は竜になると言います。このことから、世の中の裏も表も知った老獪な人は「海千山千」と表現されます。褒め言葉とはいえない表現ですが、厳しい環境をしたたかに処世してきた末の姿であります。鹿取さんの山での暮らしも、鱸の海での生き方も、「老獪」と呼べるような生き方ではないかもしれません。むしろ「海戦山戦」と呼ぶのがふさわしいのかもしれませんし、「海仙山仙」と呼んだ方がよいかもしれません。したがって、今回の嶋臺塾のタイトルは、これをあえて「海せん山せん」と書きました。柴田 三才学林長からは、この「せん」にどんな字を当てはめるか、皆さんで考えてみてください、との問いかけがあり、それをもって今回の嶋臺塾は終会となりました。(吉野 章)



第29回 地をおおうものの現在(いま)
日 時 : 平成26年3月 19日(水)午後6時~午後8時
場 所 : 嶋臺本陣ギャラリー
学堂から:「身近な大気汚染」 梶井 克純 (地球環境学堂)
信州から:「小さな苔の世界」 大石 善隆 氏 (信州大学農学部)
洛中からひとこと:「苔を思う心」阪上 富男 氏 (庭師)
司 会 : 今西純一(地球環境学堂)
主 催 : 京都大学 地球環境学堂・学舎・三才学林
協 力 : 嶋臺(しまだい)



第29回は、「地を覆うものの現在(いま)」と題し、3月19日に開催しました。学堂からは梶井克純さん、信州大学から大石善隆さん、洛中からは庭師の阪上富雄さんにご登壇いただきました。
梶井さんからは大気汚染のお話をいただきました。日本では、有害な対流圏のオゾンが、発生の原因とされてきた有機化合物が減っているのに、最近じわじわ増えてきている。梶井さんは、レーザー光線による有機化合物の計測機械を自作され、未知の原因物質を探っておられます。そでわかったことが、大気汚染の原因となる有機化合物を最も大気中に排出しているのは、なんと植物でした。人間活動の10倍ぐらいを植物が出しているのだそうです。しかし、だからといって木を切り倒してしまえという話にはならないわけで、要は、我々がゼロエミッションの世界を目指すうえで、汚染物質を減らす経路というのがあって、単純に、例えば窒素化合物だけを減らせばよいということではない、というお話でした。
大石さんからは、苔の話を聞かせていただきました。日本の庭には欠かせない苔ですが、苔を愛でる心というのは、じつは外国ではあまりなく、日本でも苔で有名な庭は京都に集中するのだそうです。苔は、陸に上がった最初の植物で、葉を覆うクチクラがありません。その葉を拡大してみるとほとんど色がありません。苔は、維管束を持たず、気孔も持ちません。葉から直接水や養分を吸収し、呼吸も行っています。こうした苔の性質は、大気の湿潤や汚染に敏感であることも意味します。苔は、自身の10倍ぐらいの水を吸収し、庭や森の水分を涵養します。森の更新にも重要な役割があります。小さな生物の生育環境でもあります。同時に、苔は環境の変化にとても敏感な植物でもあります。京都では、お寺や鎮守の森などで、貴重な苔が大事にされてきました。そうした苔をもっと知り、馴染みをもってもらえれば、といったお話でした。
また、庭師の阪上さんからは、お二人の話への感想とともに、日ごろ庭園のお仕事をされている立場から、京の山の端の景色や庭の草木のの魅力や、苔との関わりをご説明いただきました。また、会場との対話では、最近気になるPM2.5の話や、ガソリンの揮発、屋上緑化のあり方、季語としての苔など、多方面からの話題が出され、地上に暮らす私たち自身の環境を改めて考えた2時間でした。



第28回 極地を 生きる ちから
日 時 : 平成25年11月12日(火)午後6時~8時
場 所 : 嶋臺本陣ギャラリー
ヒマラヤから:「頂(いただき)へ」 竹内 洋岳 氏(プロ登山家)
京大から:「酸素がもたらす生物の進化」 高橋 重成 氏(工学研究科)
ひとこと: 竹内 裕希子 氏(熊本大学)
司 会 : 吉野 章(地球環境学堂)
主 催 : 京都大学 地球環境学堂・学舎・三才学林
協 力 : 嶋 臺(しまだい)
地球上には 標高8,000メートルを超える山が14あります。日本の登山家たちは 、それら一つ一つに敬意を込めて、神の住む場所「座」と呼ぶのだそうです。今回の嶋臺塾は、この14座すべてを、酸素補給なしで登頂された、プロ登山家の竹内洋岳さんと、空気中の酸素濃度の変化への生物の適応を研究しておられる工学研究科の高橋重成さんをお招きして、極地環境における生物の適応力について考えました。
標高が高くなると空気が薄くなります。それでも酸素濃度21%というのは変わらないのですが、空気が薄くなるので、生物が使える酸素の量は減るのだそうです。8,000メートルあたりだと、地上で換算してだいたい7%。人間がここに突然放り出されたら、すぐに気を失い、数分後には死んでしまうのだそうです。
しかし、竹内さんは、そのような環境に何度も挑んでこられました。それは、徐々に徐々に体を慣らしながら、環境に適応していく過程なのだそうです。標高5,000メートルを超えると、1,000メートル登っては、頭痛と吐き気と不眠に苛まれ、一旦戻り、再び登って、さらにその上を目指す。それを繰り返しながら8,000メートルを超えていく。竹内さんの体に特別な特徴はなく、隈なく調べたお医者さんも当てがはずれてがっかりするほどだったそうです。竹内さんからは、こうした登頂の様子について、秘蔵映像も交えながら、臨場感いっぱいでお話しいただきました。
高橋さんからは、酸素濃度の変化に生物が適応し、生物の進化とどう関わってきたかについてお話しいただきました。
地球に生物が誕生してから、地球の酸素の濃度というのは必ずしも一定していたわけではなく、大きく変動してきました。地球上に酸素が増えだしてからは、生物は、ミトコンドリアとの共生によって、生物にとってもともと毒である酸素をエネルギーに変え、同時に無毒化するというシステムを手に入れました。逆に、3億年前に地殻変動で95%の生物種が絶滅して、5,000万年におよぶ低酸素時代には、空気をため込む器官である気嚢を持つ恐竜が誕生し、その子孫である鳥類へとつながります。
酸素濃度の変動は日常でも起こり、たとえば気圧によっても変化します。酸素濃度が低くなると、応急措置として、心拍数を上げて、血流を増やすということ起こりますが、数日間それが続くと、ヘモグロビンの数が増えたり、腫瘍などで体の一部が低酸素状態になると、血管新生といって、血をたくさん巡らせるために新しい血管ができたりするのだそうです。高橋さんは、そうした酸素濃度を感知する体のメカニズムを研究されておられ、低酸素状態における応急措置にかかわるたんぱく質を調べていくと、そうした機能の獲得は、どうも哺乳類が胎盤を持つようになった時期と重なるということがわかってきたのだそうです。
竹内さんは、人間には通常あらわれていない能力の伸びしろのようなものがあり、極限状態にあるとそれが発揮されるのではと言われます。わらわれ地球環境学にかかわる研究者たちは、気候変動や生物多様性の保全といったものへの関心の高く、人類は生き残れるのかということが議論されますが、竹内さんや高橋さんのお話は、これから何万年後、人類はどのような能力を獲得していくのだろうかという、いつもとは違う話題で、少し嬉しい違和感を感じられる今回の嶋臺でした。
最期には、竹内さんの妹さんであり、最近まで地球環境学堂におられた竹内裕希子さんにもご登壇いただき、お兄さまの幼少時代のお話も交えたとりまとめをいただくなど、和やかな会となりました。(吉野 章)
第27回 鮎香る川
日 時 : 平成25年7月30日(火)午後6時~8時
場 所 : 嶋臺本陣ギャラリー
嵐山から :「京料理と鮎」 栗栖 基 氏 ( 熊彦主人 )
学堂から:「石垢と鮎」 宮下 英明 (地球環境学堂 教授)
洛中からひと言、ふた言 ...
司 会 : 深町 加津枝 (地球環境学堂 准教授)
主 催 : 京都大学 地球環境学堂・学舎・三才学林
協 力 : 嶋 臺(しまだい)



夏の京料理には欠かせない鮎。その鮎の棲む川が減ってきています。そのことは、私たち日本人に何を教えているのでしょうか。今回は、京料理界から嵐山の熊彦のご主人・栗栖さんと、学堂の宮下教授にお願いして、鮎について語ってもらいました。
栗栖さんからは、京料理の歴史から食材としての鮎の特徴、食べ方についてお話いただきました。四里四方の食材を大切にする京料理において、川魚は切り離すことができない食材で、その中でも鮎は夏の川魚の代表です。初夏の稚鮎の天ぷら、小鮎の時期の背ごし、成魚の塩焼き、そして秋口の落ち鮎の煮つけといった、年魚である鮎の成長に沿った食べ方や、「うるか」のおいしさ、友釣りで釣り上げた鮎の扱い方等々、料理人ならではのお話を、美しいお料理の写真とともに聞かせていただきました。そのことを通して、私たちがいかに鮎という食材を愛してきたか、日本人と鮎との関わりについて知ることができました。
宮下さんからは、鮎を育む川とはどのような川かについてお話しいただきました。宮下先生は、藻類の研究者で「鮎は専門ではない」と言いながら、鮎が餌を食べる映像なども交えて、鮎の生態についてわかりやすく教えていいただきました。鮎の餌は、タンパク質が豊富で消化しやすい藍藻、ビロウドランソウなのだそうです。この藍藻は、渕や平瀬、早瀬など、地形が複雑で岩が転がった、きれいな水が速く流れる、そういう川で育ちます。護岸が整備され流れの安定した川では、ガラス質で栄養価の乏しい珪藻や、消化できない緑藻しか育たないそうで、そうした川に鮎は棲むことはできません。
京料理という完成された食文化も、食材を育てる川あってのことで、その川は、生きものそのもの、水質や流量だけ維持しても意味がない、ましてや川を「水を流す道具」程度にしか考えられないようではいけないことを、改めて知らされた今回の嶋臺塾でした。(吉野 章)




第26回 甍(いらか)の波をおよぐ
日 時 : 平成25年3月22日(金)午後6時~8時
場 所 : 嶋臺本陣ギャラリー
淡路島から:「カワラぬ価値を想う」 道上 大輔 氏(瓦師)
大学から : 「伝統構法を未来につなぐ」 鈴木 祥之 氏(立命館大学 教授)
洛中からひと言、ふた言 ...
司 会 : 吉野 章(地球環境学堂 准教授)
主 催 : 京都大学 地球環境学堂・学舎・三才学林
協 力 : 嶋 臺(しまだい)



第26回は、瓦と伝統的な建築について考えました。平成7年の阪神淡路大震災以来、瓦の需要は激減しました。瓦で重い屋根は潰れやすいという風説の定着が、その理由だと言われています。震災当時、押しつぶされた瓦屋根の映像が、テレビから幾度となく流されました。
今回お話しいただいた道上さんは、淡路瓦の職人さんで、このような状況に危機感を抱き、瓦の価値を訴えるために、さまざまな取り組みをされている方です。ご自身のギャラリーに置かれた瓦の椅子や、国内外の瓦のある風景、取り組みとして行われている火入れ式の様子など、美しい写真を紹介しながら、瓦は、1000年以上に亘って、日本の風土の中で培われてきた守るべき伝統的価値であること、そのことは、瓦の需要が落ち込んだ現在でも変わることはなく、瓦の曲線や瓦屋根の風景が、日本人の美意識の奥に眠っていること、だから、感性に訴えると、若い人にも瓦の価値を思い出してもらえるのであって、古き良き町並みを守ることに留まらない、「新しき良き町並み」づくりをやるべきであるし、それを目指しているのだ、ということを熱く語られました。
鈴木先生からは、瓦屋根の耐震性を構造力学的にどう評価できるか、平易な言葉で解説いただきました。また、伝統的な京町家と新しい町家風の家を、実際に振動台に載せて揺らした映像を使って、それぞれの揺れ方の違い、崩れ方の違いを見せてもらいました。そうした上で、伝統的な建物の耐震をいかにすべきか、巨大な瓦屋根をもつ東本願寺御影堂の耐震補強の様子なども交えて説明されました。そもそも木造建築の軸組構法には、伝統的構法と在来工法というのがあり、在来構法が、建築基準法の仕様規定に沿ってつくられるのに対して、伝統構法はそうした仕様を見たさないので、限界耐力計算という方法で、仕様規定と同程度以上の耐震性を満たす性能を示さなければならないそうです。しかし、そのための手続きの煩雑さは、一般の工務店が処理できるものではなく、伝統構法を守るためには、建築基準法の見直しが必要とされています。鈴木さんは、阪神淡路大震災以来、木造建築の耐震性の評価や、補強、設計を研究してこられ、現在、その制度的見直しを進めておられます。そうした取り組みの現状についても紹介いただきました。
会場からは、京町家で暮らして、京の町並みの変遷を見てこられた方や、町並みづくりに携わっておられる方など、多彩な見解や質問が出され、いつも以上に厚みのあるやりとりが行われました。議論は尽きることなく、惜しみながらの閉会となりました。(吉野 章)
第25回 虫に聴く
日 時 : 平成24年12月3日(木)午後6時~8時
場 所 : 嶋臺本陣ギャラリー
山城から: 「虫送りのいまむかし」 濵口 洋 氏(日本農薬株式会社 顧問)
京大から: 「虫の ちえ に学ぶ」 梅田 真郷 氏 (工学研究科 教授)
寸 評 : 加藤 真(地球環境学堂 教授)
司 会 : 清中 茂樹(地球環境学堂 准教授)
主 催 : 京都大学 地球環境学堂・学舎・三才学林
協 力 : 嶋 臺(しまだい)




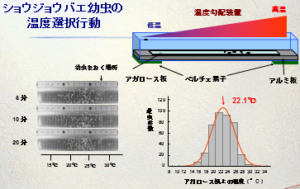





第24回 森を看る
日 時 : 平成24年7月28日(木)午後6時~8時
場 所 : 嶋臺本陣ギャラリー
挨 拶 : 藤井 滋穂(地球環境学堂長)
学堂から: 「熱帯の森を喰らう」 岡田 直紀(地球環境学堂准教授)
洛中から: 「京の里山をいける」 笹岡 隆甫 氏(未生流笹岡家元)
ひとこと: 横山 俊夫 (京都大学名誉教授)
司 会 : 深町 加津枝(地球環境学堂 准教授)
主 催 : 京都大学 地球環境学堂・学舎・三才学林
協 力 : 嶋 臺(しまだい)



第24回嶋臺塾のテーマは、「森を看る」でした。
学堂の岡田さんからは、マレーシアのクンダサンで栽培された野菜、アブラヤシのプランテーションからのパームオイル、マングローブ林で養殖されたエビについてのお話を頂きました。これらの事例が物語るのは、熱帯の森の恵みを食べるのではなく、熱帯の森を破壊して、そこで生産したものを食べる。そして、収奪をして間接的に食べるというものでした。それはまさに「熱帯の森を喰らう」私たちの日常生活そのものであり、食べること、使うことを通して、実は熱帯の森を破壊し、その地域の生態系の健全性や人々の生活や文化に結びつかない産業の実態でした。
華道未生流笹岡の家元である笹岡さんは、まず、生け花には「足でいけよ」という教えがあり、身近な京の里山に足を運び、その自然の姿に目を行き届かせて看ることが重要であると力説されました。そして、生け花は哲学であり、自然というものについて考えることであり、花をいをいけることは、祈りや願いといった人間の思いから始まっているというお話を頂きました。さらに、生け花など文化芸術の役割は、今まであるものを守っていくだけではなく、それをどのように新しいものへと変えていくかという挑戦の連続であることを、平等院鳳凰堂での生け花を事例にご紹介頂きました。
来場者を交えた対話では、「喰われた森」にどのように向き合うべきかという問いに、地元の住民の利益を保証しつつ、私たちが身を切るようなことをいとわずに知恵と労力を出し、時間をかけていくことが大切、との岡田さんからの答え。さらに「ただ、現実は厳しい」との一言 けることは、祈りや願いといった人間の思いから始まっているというお話を頂きました。さらに、生け花など文化芸術の役割は、今まであるものを守っていくだけではなく、それをどのように新しいものへと変えていくかという挑戦の連続であることを、平等院鳳凰堂での生け花を事例にご紹介頂きました。
また、来場者より笹岡さんのハスの生け花、巻き葉、朽ち葉のお話をふまえた五行詩が披露されました。それに対して、里山での歴史を振り返れば、意外と上手に自然とつき合ってきた「日本人の暮らしぶり」というのがあり、そこから教わるべきことは大いにあると感じています、との笹岡さんの言葉。
最後に、手をかざして、手の下で目を見開き、じっと見つめて、全体をとらえているお二人の姿勢が、分野をこえ「森を看る」ところでうまくつながった、という寸評で締めくくられました。(深町 加津枝)





第23回 つむぐ、まとう
日 時 : 平成24年3月28日(水)午後6時~8時
場 所 : 嶋臺本陣ギャラリー
学堂から:「人生を彩る衣~ 印度の絞り染め」 金谷 美和(三才学林 研究員)
世界から: 「環境にやさしい素材づくり ~ 製品の一生を考える」岡 研一郎 氏(東レ株式会社 地球環境事業戦略推進室長)
ひとこと: 横山 俊夫(人文科学研究所 教授)
司 会 : 吉野 章(地球環境学堂 准教授)
主 催 : 京都大学 地球環境学堂・学舎・三才学林
協 力 : 嶋 臺(しまだい)



多くの方々にお集まりいただき、今年度最後の嶋臺塾は、衣食住の衣をテーマに語り合いました。
金谷美和さんのインドの絞り染めのお話しは、「布は身に纏って初めて意味をなす」という言葉から始まりました。インドのカッチ地方では、女性が絞り染めの布を頭から被り、顔を隠すという使われ方をされているそうです。会場にお越しの女性に、実際に絞り染めを被っていただくと、布に施された円は女性の腰のあたりにバランスよく配置され、被ることによって生まれた襞が美しい陰影を作り出しました。この被り布は、既婚の女性が夫が健在な間、身に纏うことができる衣だとのこと。結婚式の時にも布を被り、布の四隅には邪視を避けるため4のつの品が括りつけられているそうです。この他にも絞り染めの工程や布の役目についてお話しいただき、人生や社会と結び付いた布の意味を知ることができました。
岡研一郎さんからは、新しい繊維とLCA(ライフサイクルアセスメント)についてお話しいただきました。LCAとは、製品が生まれてから処分されるまでの一生涯を対象に評価すること。製造過程だけでなく、製品の一生涯を通して考えることによって、環境への影響を客観的、定量的に評価できるようになります。種類の化繊の特徴を組み合わせて作られた新開発の下着は、身体から出ている水蒸気を吸って冬でも暖か、しかも着心地がよく、お洒落であるため大ヒット商品となっているそうです。LCAによってこの新しい下着の評価を行ってみると、ひと冬、綿の下着の代わりに着用すると、50年生のスギ1本が1年で固定する量のCO2を削減する効果があることがわかったそうです。航空機の機体に用いられる炭素繊維は、3,000度の高温で焼いて作るため、製造の過程で大量のCO2を排出するのですが、機体の軽量化による航行時のCO2削減効果の方がずいぶんと大きく、製品の一生涯を考えれば、従来の金属製の機体を用いるよりも環境にやさしいということでした。
来場者を交えた対話では、天然繊維と合成繊維についての議論がありました。綿や麻などの天然繊維は、一見すると合成繊維よりも環境にやさしそうですが、生産に土地を必要とするため食糧生産と相反する面があることや、大量生産のために窒素肥料や農薬を用いるため環境へ悪い影響を与えている面があることの指摘がありました。一方で、合成繊維は石油に由来するため、先行きが不透明であり、環境に負荷を与えていることには違いありません。これからは、バイオマスに由来する繊維の製品化や、布を大切に最後まで使いまわしていたかつての暮らし方を見直すことが大切ではないかとの意見が出されました。江戸時代には、着物に対する規制があったために、文化が発展したという側面もあるとのこと。衣にまつわる自由な創意によって、よりよい環境となることを願って、今回の嶋臺塾は幕になりました。(今西純一)



第22回 京から食をみなおす
日 時 : 平成23年12月7日(水)午後6時~8時
場 所 : 嶋臺本陣ギャラリー
学堂から:「食が支えるお腹の共生系」 谷 史人(地球環境学堂 教授)
南禅寺門前から: 「とうふ処 京都のこれから」おかべ家 上田 成人 氏( とうふ家)
司 会 : 松本 泰子 (地球環境学堂 准教授)
主 催 : 京都大学 地球環境学堂・学舎・三才学林
協 力 : 嶋 臺(しまだい)



第22回嶋臺塾は、2011年度2回目ということで、「食」がテーマとなりました。学堂の谷さんからは、食と腸内細菌との関係についてお話しいただきました。人間のお腹の中には、300~500種類の腸内細菌がいて、その数は、宿主である人の細胞数よりもたくさんなのだそうです。どんな腸内細菌が棲みつくかは、何を食べているかで決まるのだそうですが、これは人の生体防御や消化機能と深く関わっているので、お腹の中から食べるものを考えることも大切だというお話でした。洛中・南禅寺門前からは、とうふ家の上田さんから、とうふの歴史とこれからのとうふについてお話いただきました(「とうふ家(toufu-ka)」は、上田さんが考えた、とうふの可能性に挑むひとの意をこめての呼称)。中国で生まれて、遣唐使によって日本に伝えられたとうふは、京都のお公家さんや寺社の厳しい要望に応えながら、江戸時代には、その製造技術が究極にまで洗練されたのだそうです。しかし、一時は全国5万軒に達したとうふ屋さんの数も、現在は1万軒にまで減少してしまいました。これからの日本の食の中で、どのようにとうふが生き残っていくかについての柔軟な発想と実践の必要性について、とうふ家のお立場からのご自身の取り組みも交えての、熱い思いをお聞かせいただきました。お二人の対談では、「とうふがお腹によいことは、長年食べてきた日本の誰もが知っているが、そのことについて、現代科学はどのような言葉で語っているのか?」との上田さんの問いに、それこそ現在進行中の大切な研究テーマであるとの答え。結果が期待されます。何を食べてきたかでお腹の中が決まり、お腹の中しだいで何を食べるべきかが決まる、ということで、食を、機能性からだけでなく、文化として考えることがのぞましいということを再確認し、とうふと日本人の関係を改めて考えさせられました。会場からも、自分の腸内細菌を心配した質問や、とうふについての素朴な疑問など、多数の質問が出て、和やかで活気のある集いとなりました。(吉野章)





第21回 京のしまつ・世界のしまつ
日 時 : 平成23年7月6日(水)午後6時~8時
場 所 : 嶋臺本陣ギャラリー
挨 拶 : 前 一廣(三才学林長)
学堂から: 「しものふん別」原田 英典(地球環境学堂特定助教)
洛中洛外から:「京のこやし咄」森谷 尅久氏(歴史家 )
司 会 : 藤田 健一(地球環境学堂)
主 催 : 京都大学 地球環境学堂・学舎・三才学林
協 力 : 嶋 臺(しまだい)



2011年度は、私たちのくらし(衣・食・住)をテーマにとりあげ、3回開催する予定です。最初の7月6日は、生命活動にともなう排泄物という大切なことにもかかわらず、日頃話題に上ることの少ない「しものしまつ」の話でした。まず、前一廣三才学林長の挨拶のあと、学堂の原田英典さんから「しものふん別」と題してお話がありました。し尿を分別し、かつて日本でも利用していた下肥のように農業循環はできないか、尿から貴重な資源であるリンをうまく回収できないか、などいくつかの問題提起がありました。そして、東北の被災地の復興の一助として設計された緊急用し尿分離型トイレについて臨場感あふれる報告。その中で、トイレの問題は、衛生の確保の問題であると同時に、人間の尊厳の確保の問題であるという原田さんのご発言が印象に残りました。
ついで、洛中洛外から歴史家の森谷尅久さんの「京のこやし咄」と題するお話がありました。京の中心部のし尿を肥桶に入れて農村へと運搬して資源活用し、逆に農村からは野菜が供給されるなど、中世の京都と周辺地域との間で権利関係とともに確立していた、し尿を基軸とする循環システムについて貴重なお話をうかがいました。
最後に、会場にお越しいただいた70名を超える方々と活発な意見交換がありました。土壌の専門家からは、下水処理インフラを一から作り直す必要に迫られている地域だからこそ可能な、し尿を分離してリンを回収するシステムを東北の被災地の復興に組み入れることを考えるべきとのエールをいただき、拍手が沸き起こりました。(松本泰子)